こんにちは!ikkiです。
みなさん資格勉強などの勉強の際、効果的な復習はできていますか?
多くの方が私と同じように、効果的な復習方法がわからず、とりあえず解答読んで理解して、問題をたくさん解く、、、みたいな感じになっているんではないでしょうか。
もちろん人によって最適な復習方法は異なるかと思いますが、今回はその一つの答えとなるノウハウ「具体化と抽象化」についてお話ししていきます。
あなたの復習効果U Pに役立つこと間違いなしです!
復習で陥りがちな罠
「間違えた問題の復習は大切」
これは小学校くらいから、親や先生に言われ続けている言葉だと思います。
ですが、具体的にどのように復習したらいいかは教えてもらえず、多くの方が自己流でやってこられたと思います。
そんな中で、復習でやってしまいがちなあるあるを紹介しましょう。
- 解答を見て「あーなるほど」と思い、次の問題に移る
- 解答を丸暗記
- 次に同じような問題でたら気をつけようと思う(思うだけ笑)
「あー、確かに」と思われた方、いらっしゃるんではないでしょうか?
これらは復習としての効果をほとんど成していません。
本番で全く同じ問題が出たら解けるかもしれませんが、ちょっと応用されたらほぼ対応できないでしょう。
かく言う私も復習がとても苦手です。
経験値を積むためにより多くの問題を解かなければいけないという焦りから、つい復習をおろそかにしてきました。
昨年、国家資格である中小企業診断士試験に挑戦したのですが、ここで復習力の弱さを露呈してしまいました。
記述式である2次試験の対策では、間違えた問題の復習はまさに上のリストと全く同じ状態。
いざ試験当日を迎え、問題と向き合うも、もちろん試験対策と同じ問題などでるはずもなく、復習が実践に全く生きません。
そして、「同じような問題が出た!」と思っても、あやふやな記憶から思い出すのに時間がかかってしまいタイムロス。
結果は不合格
結果発表直後は何が悪かったのかがはっきりせず、とても悶々とした日々を過ごしていました。
そんな中、このままでは来年受けても同じ結果になってしまうと思い、来年の受験に向けて情報収集をしていたところ、この「具体化と抽象化」と言う最高の復習術を見つけたので、是非みなさんに共有したいと思います。
具体化と抽象化
そもそも具体化と抽象化とは何でしょうか。
具体化:
- 抽象的な事柄を形にして表すこと
- 理想や考えを実際の形やものにして実現すること
- 現実化すること、または現実らしく見せること
例)「りんご」を具体化 → フジ、ジョナゴールド、王林 etc.
抽象化:
- 個々の具体的なものから共通の属性を抜き出して、一般的な理念をつくること
- 重要ではない細部の情報を取り除き、物事の本質を捉えるための思考法
例) 「りんご」を抽象化 → 果物、赤いもの、植物、食べ物 etc
定義は広辞苑より抜粋
つまり具体化とはより詳細なものへ、抽象化はより範囲が広いものへ変換していくことになります。
「細かく見ろ」とか「広い目で見ろ」と言われることはあるけれど、正反対の意味合いを持つこれら2つを、どのように活用すればいいのでしょうか。
では次に、「具体化と抽象化」を復習に生かすノウハウをお伝えしましょう。
間違えた原因を「抽象化」
あなたはある問題を間違えました。
解答を見ると、問題に取り組んでいる際には気づかなかった解法や解答例が書いてあります。
いつものように「あーなるほどね、ここをこうすればよかったんだ」で終わらせていてはダメです。
これでは全く同じ問題が出た場合にしか対応できません。
まずはダメだった理由を抽象化していきましょう。
【問題】Aのメリットについて2つ答えよ
【解答】〇〇と△△
→あなたは〇〇だけしか答えることができませんでした。
×:Aのメリットは△△もあるんだ。覚えておこう
○:Aの代表的なメリットは3つあるけど、そのうちの1つしか覚えれていなかった。そもそもAのメリット、デメリットについてきちんと整理できていないことが原因だったので、そこを整理してみよう。
このように間違えた原因を抽象化(範囲の広いものに変換)することで、より幅広い範囲の問題に対応できるようになります。
これは試験問題だけでなく、仕事やスポーツ、趣味などで新しいことに挑戦する際にとても重要な考え方です。
何事ものみ込みが早い人は、無意識のうちにこの思考を行えているので、人一倍吸収が早く、どんどん成長していくと言われています。
間違えや失敗の原因を抽象化して考える
覚えておきましょう!
次回への対策を「具体化」
次は対策の「具体化」です。
よくない対策の一例が、
「次は答えられるように頑張ろう!よし次の問題へ、、、」
ここまではひどくないと言う人もいるかもしれませんが、意外と同じようなことをやっている人は多いです。
対策の肝は、具体的に行動できるレベルまで落とし込むことです。
例えば、よくある「間違っているものを選べ」の問題で、「正しいもの」を選択するというミスを犯した場合。
×:次は間違えないように気をつけよう
○:制限時間に焦ったことで、問題文をきちんと読んだつもりになっていた。(間違えた原因の「抽象化」)→次からは問題文中の「正しいもの」、「間違っているもの」の箇所を○で囲むようにしよう。(対策の「具体化」)
このように間違えた原因の抽象化と合わせて行うことで、復習の効果を一気に上げることができるます。
「いちいちそんな回りくどいことできないよ!問題は何回解いたかが勝負でしょ!」
このような考えも否定はしませんが、次のように考えてはどうでしょう。
- きちんと復習せずに1問解くのにかかる時間が5分、得られる経験値は3。
- きちんと復習して1問解くのにかかる時間は15分、得られる経験値は10。
10時間勉強した時に得られる経験値は、1の場合360、2の場合400。
復習の仕方によってはこの経験値を2倍、3倍にできるので、差はどんどん大きくなっていきます。
これは、自分が資格試験の勉強をしていて実感したところなので、騙されたと思ってぜひ実践してみていただきたいです。
まとめ
今回は効果的な復習のノウハウとして「具体化と抽象化」についてお話ししました。
間違えてしまった原因を抽象化し、対策を行動できるレベルまで具体化する。
これを意識するだけで、復習の効率は何倍にも上がっていきます。
現在新しいことへの挑戦として資格試験などに挑まれている方には、ぜひとも取り入れていただければと思います。
かくいう私も、この理論を実証するためにも、今年の中小企業診断士試験に絶対合格したいと思います。
みなさんも一緒に頑張りましょう!
ではまた!
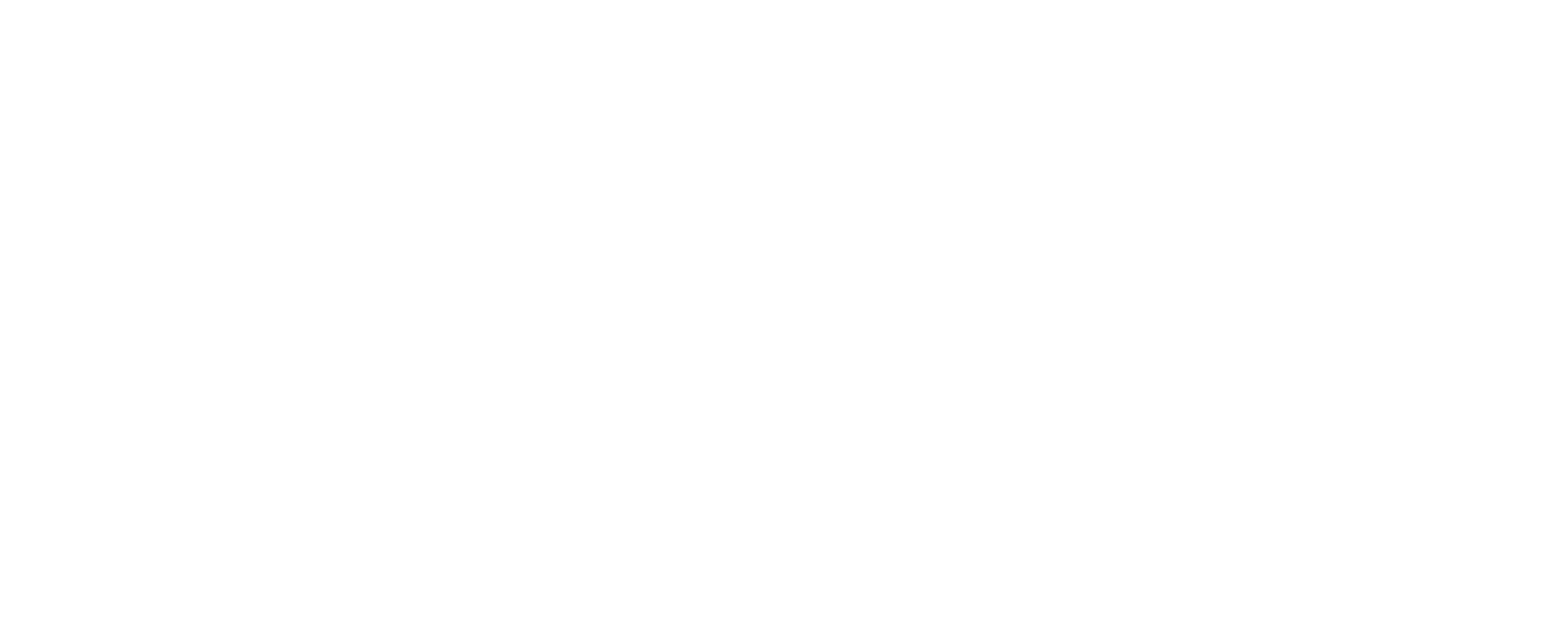







コメント