こんにちは!ikkiです。
今回は、書籍『7つの習慣』より、後半戦①として第四の習慣〜第五の習慣について紹介してきたいと思います。
前半戦の第一の習慣〜第三の習慣についてはこちらの投稿にて紹介しております。
また、この書籍については、以下の記事で紹介していますので、是非覗いてみて下さい。
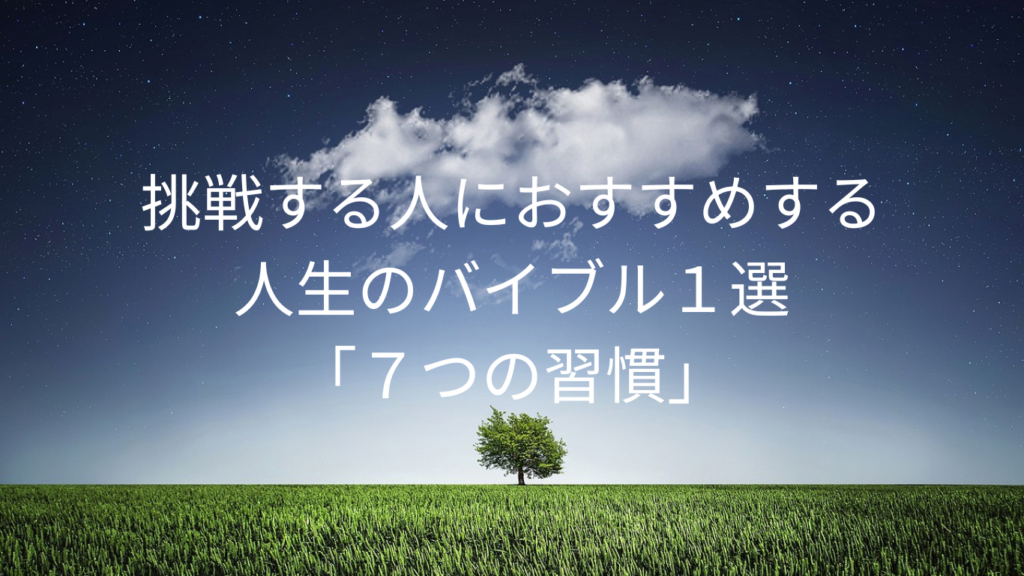
『7つの習慣』とは
アメリカのスティーブン R. コヴィー博士(以後コビー先生と呼ばせていただきます。)が書いたベストセラービジネス本。
真の成功に辿り着くのに必要な7つの習慣を紹介してくれています。7つの習慣とは以下の通りです。
- 第一の習慣 主体性を発揮する
- 第二の習慣 目的を持って始める
- 第三の習慣 重要事項を優先する
- 第四の習慣 WinWinを考える
- 第五の習慣 理解してから理解される
- 第六の習慣 相乗効果を発揮する
- 第七の習慣 刃を研ぐ
このうち第一〜第三の習慣を身につけることで、個人として成功を収めることができ、第四〜第六の習慣を身につけることで、公的な成功(他者を巻き込んでの成功)を収めることができます。
そして第七の習慣でこれらを磨き続けることで、長期的な成功、つまりは真の成功を収めることできると言うものです。
これから新しい何かに挑戦される方に是非とも読んでいただきたい1冊です。
第四の習慣「Win-Winを考える」
公的な成功を収める上でまず大切となってくるのが、よく言われる「Win-Win」な状態を考えることです。
コビー先生は人間関係は以下の6つに分類されると言います。
- Win-Win :自分も勝ち、相手も勝つ
- Win-Lose :自分が勝ち、相手は負ける
- Lose-Win :自分が負け、相手が勝つ
- Lose-Lose :自分も負け、相手も負ける
- Win :自分だけの勝ちを考える
- Win-WinまたはNo Deal :Win-Winの合意に至らなければ取引しない
相手とのコミニュケーションを重ね、常にWin-Winとなるように心がけたいところですが、もちろん世の中そんなには甘くなく、相手次第では達成できないこともあります。
そのため、最後の「Win-WinまたはNo Deal」の考え方を持つことが大切になります。
どちらかが損だと思うくらいなら、無理して取引しないのです。
ですが、人は多くの場面でついついWin-Loseの考えで打ち負かしたり、Lose-Winの考えで妥協したりしがちです。
これは部活や受験戦争、効率よく決めるための多数決の文化などから「勝つ人がいれば負ける人もいる」という考え方が刷り込まれているんでしょう。
人は自分を打ち負かした人に再度お世話になろうとは思わないですし、逆に打ち負かした相手にはまた打ち負かしてやろうと思ってしまいます。
これから長く付き合っていきたいと思う相手であるほど、お互いのWinを達成できる落とし所を探す癖をつけていきたいですね。
そしてここで一つ大切なのが、相手の本当のWinを知るということです。
これはWin-Winでしょ!と思った行動が、相手にとっては全然Win-Winじゃないということはよくあります。
例えば、親が子供に対して「将来、いい会社に入るためにも、たくさん勉強していい学校にいきなさい!」と言ったとします。
これは、親にしてみれば「子供の人生を成功に導く」という自分のWinと、「将来いい会社に入って成功する」という子供のWinを達成することを思っての言葉でしょう。
ですが、後者は本当に子供にとってのWinなのでしょうか?
本当はやりたいことがあって、そのためのスキルが身につけれる別の学校に行きたいと思っている可能性もあります。
本当のWin-Winを達成するためには、第五の習慣にもつながりますが、相手を理解するということを忘れてはいけません。
まずは相手の本当のWinを理解し、その上でWin-Winを考える。
そんな素敵な習慣を、今からでも心がけていきましょう!
第五の習慣「理解してから理解される」
第五の習慣はコミュニケーションにおいてとても重要です。
コミュニケーションの鉄則は、「まずは相手を理解するように努め、その後で自分を理解してもらうようにする」です。
みなさんも自分のことを全く理解してくれていない人に、「俺の言うことを理解しろ!」と一方的に言われても、聞く気になりませんよね。
相手を理解すると言うことは相手の話を聞くことから始まりますが、コビー先生は相手が話しているとき、私たちは次の五つのいずれかのレベルで聞いているといいます。
- 無視する: 聞いていない
- 聞くふりをする: 相槌を打つだけ
- 選択的に聞く: 会話の部分部分しか耳に入れない
- 注意して聞く: 注意深く集中して相手の言葉を聞く
- 感情移入してきく: 心の底から理解するつもりで聞く
多くの人が1〜4の聞き方をしていて、5で聞くことはほとんどありません。
ですが、相手を本当に理解するためには、相手の立場から物事を眺め、相手の見え方、感じ方を理解する感情移入をした上で話を聞くことが非常に大切になります。
一方で多くの人が、人の話を聞くときに陥ってしまうのが、自叙伝的な聞き方です。
自叙伝的な聞き方とは、ついつい相手の状況を自分と重ね合わせて話を聞いてしまい、自分の過去の経験に基づいた返答をしてしまうことです。
「その考えは間違えだ。」→【評価】
「本当にちゃんと調べた?」→【探り】
「そういうときは〇〇〇すべきだよ。」→【助言】
「それは⬜︎⬜︎⬜︎だから、もっと▲▲▲したほうがいいと思うな。」→【解釈・助言】
このように評価、探り、助言、解釈といった返答がコミュニケーションにおいて重要なこともありますが、こと相手を理解するということにおいては弊害になってしまいます。
でも実際これをせずに話を聞くのはめちゃくちゃ難しいです。
私も、「相手の話をまずちゃんと聞こう!」と思っていても、ついつい解釈や助言の返答をしてしまいます。
「こんなの現実的じゃない!」と思ってしまうかもしれませんが、営業のトップセールスや敏腕のカウンセラーの方などは、5の聞き方が非常に優れているといいます。
いきなり全部をやろうと思うことは難しいかもしれませんが、まずはあなたの一番大切な人に対して、可能な限り感情移入して聞くことを試してみましょう。
きっと、それによって相互理解が高まり、これまで以上の良好な関係を育むことができるはずです。
まとめ
いかがだったでしょうか。
今回は『7つの習慣』より第四〜第五の習慣を紹介させていただきました。
相手とのWin-Winを常に意識し(第四の習慣)、自分を理解してもらおうと思うのであれば、まずは相手を心底理解することに努める(第五の習慣)。
どちらも当たり前のようで、実践するのはなかなか難しい習慣です。
できることから少しずつでも構いません。
変わるために何か行動を起こす。その一歩が確実な財産になると私は思います。
さあ、今から昨日までとは違う習慣を身につけてみましょう!
ではまた!
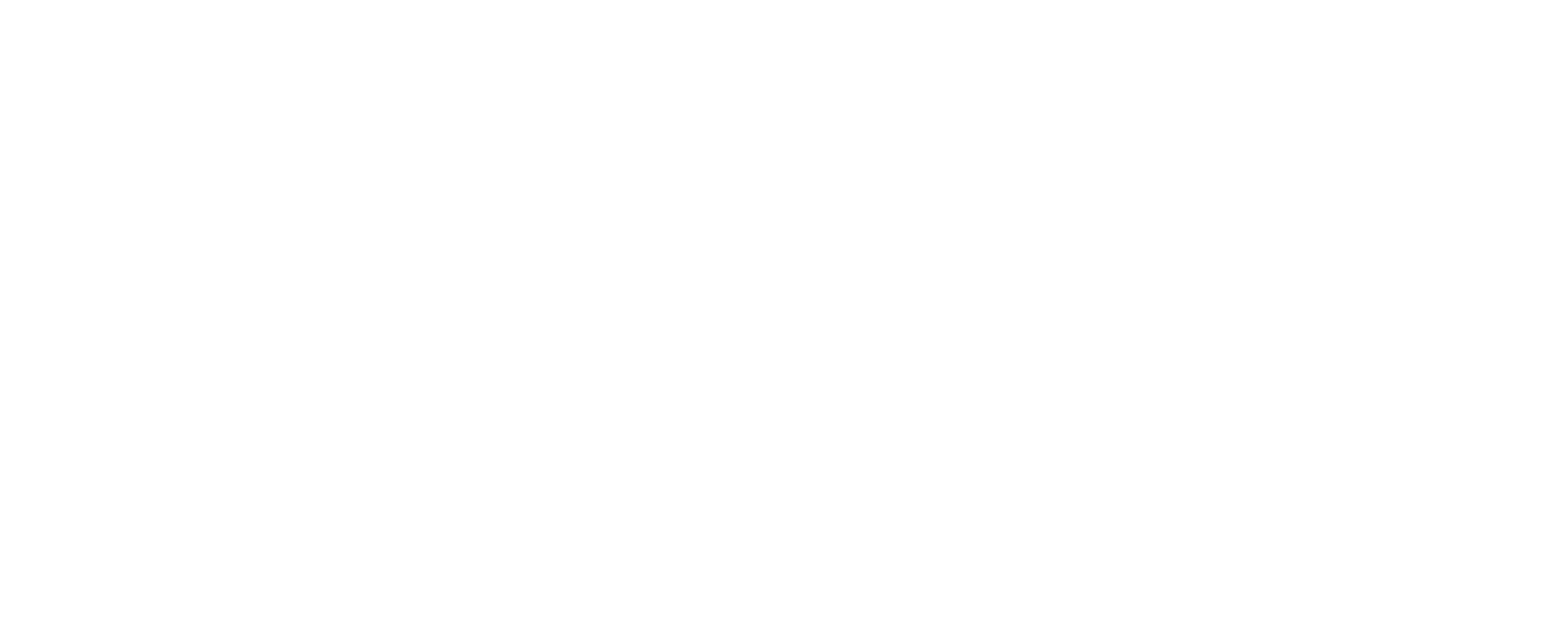





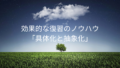
コメント