こんにちは!ikkiです。
今回は、書籍『7つの習慣』より、第一の習慣〜第三の習慣について、私の実体験なども踏まえながら紹介してきたいと思います。
この書籍については、以下の記事で紹介しております。
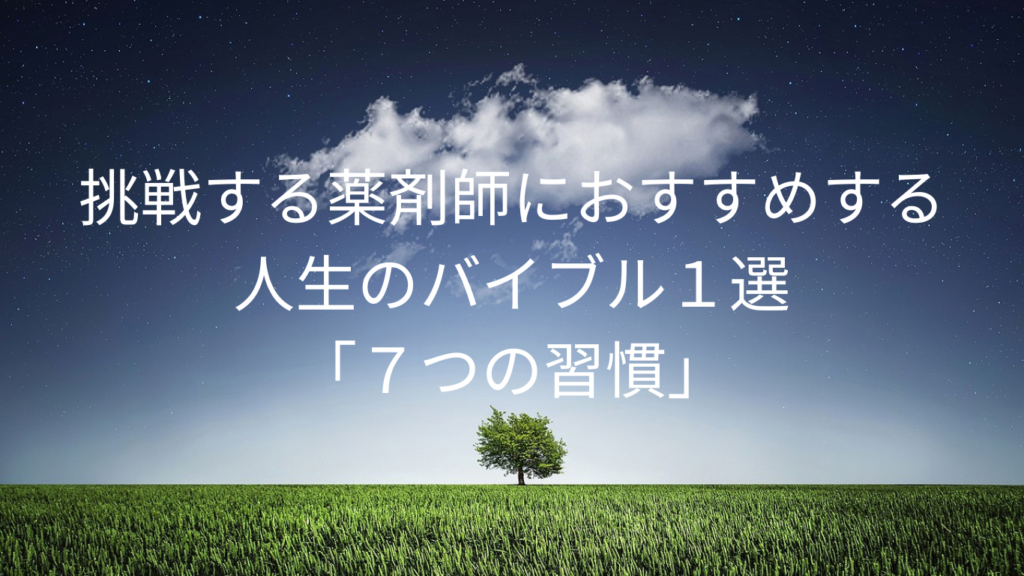
『7つの習慣』とは
アメリカのスティーブン R. コヴィー博士(以後コビー先生と呼ばせていただきます。)が書いたベストセラービジネス本。
真の成功に辿り着くのに必要な7つの習慣を紹介してくれています。7つの習慣とは以下の通りです。
- 第一の習慣 主体性を発揮する
- 第二の習慣 目的を持って始める
- 第三の習慣 重要事項を優先する
- 第四の習慣 WinWinを考える
- 第五の習慣 理解してから理解される
- 第六の習慣 相乗効果を発揮する
- 第七の習慣 刃を研ぐ
このうち第一〜第三の習慣を身につけることで、個人として成功を収めることができ、第四〜第六の習慣を身につけることで、公的な成功(他者を巻き込んでの成功)を収めることができます。
そして第七の習慣でこれらを磨き続けることで、長期的な成功、つまりは真の成功を収めることできると言うものです。
どれも結構ハードな習慣ですが、これらを身につけることができた日には、皆さんも真の成功者に近付いていることでしょう。(私はまだまだですが、、、)
第一の習慣「主体性を発揮する」
主体性を持って自らの意思で選択し、そして自分の人生の責任を引き受ける。それが第一の習慣であり、全ての習慣の基礎となります。
私がこの項で一番印象に残ったのは「影響の輪」と「関心の輪」についての話です。
「関心の輪」とは、単純に関心がある事柄です。
健康や家族、仕事の問題、経済についてなど、人によってそれぞれ違います。
「影響の輪」とは、その中でも自分が影響を与え、コントロールができる事柄のことです。
図にするとこんな感じです。(『7つの習慣』より一部改変)

では、このうちどの領域にエネルギーを注ぐべきかわかりますか?
もちろん、自身がコントロールすることができる「影響の輪」に注ぐべきです。
ですが、人間はついつい「影響の輪」の外の「関心の輪」にエネルギーを注ぎ、何も解決できないまま疲弊してしまう癖があります。
「なんであいつは今日あんなに機嫌が悪いんだろう。顔を見るだけでイライラする。」
「あの芸能人、また不祥事を起こしたのか!許せんわー。Xで叩いとこ。」
もちろん関心の輪にエネルギーを注いではいけないと言うわけではありませんが、時間やエネルギーは有限です。
主体性のある人は、できるだけ「影響の輪」に働きかけ、結果として「影響の輪」をどんどん広げていきます。
この話を聞いた時に、自分がいつも悩んだり、感情を振り回されていることの多くが、「影響の輪」の外の事柄であることに気がつきました。
そして、そんなことにエネルギーを注ぐよりは、自分が変えることができる「影響の輪」の中の事柄に注力しようと思い立った時、なんだか肩の荷がふと軽くなるのを感じました。
皆さんも今思い悩んでいること、エネルギーを注いでいることが、どの領域にある事柄なのか一度整理してみて下さい。
そして、できる限り「影響の輪」に入る事柄に注力し、主体性を高めていきましょう。
第二の習慣「目的を持って始める」
第二の習慣では、以前の投稿でも紹介した、「自分の葬儀の弔辞で言ってもらいたい言葉が、自身の基礎的な価値観であり向かうべき方向性である。」と言う話が冒頭で紹介されています。
この内容はとても刺さるものであり、今後の進路を考える上で大いに影響をうけました。
もう一つ、この項で印象に残った言葉が
全てのものは2度つくられる
です。
料理に例えると、みなさん料理を作る時、まず出来上がりの状態を想像してから調理を開始しますよね?
「この具材があるからとりあえず切って、焼いて、余ってる調味料をいれたものを食べよう。」
という方はあまりいないと思います。
この出来上がりの状態を創造することが第一の創造であり、具材を調理することが第二の創造です。
つまり第一の創造を行わずして、第二の創造を成功させることはできないのです。
ですが人間はついつい第一の創造を疎かにしがちです。
例えとして、リーダーシップとマネジメントについて考えてみましょう。
現場を効率よくやりくりするマネジメントは第二の創造、向かうべき方向性を決めるリーダーシップが第一の創造です。
そして、現場では往々にして、目先の業務をこなしていくためのマネジメントが重視され、長期的な方向性を決めるリーダーシップが軽視されがちです。
これによって、向かうべき方向性を意識していない、効率性だけを重視した機械集団ができてしまい、気がついたら泥沼にハマっていたり、なんのために働いているのかわからなくなってしまうことがあります。
長期的にみた成功(解決)を得るには、リーダーシップを大切にし、それにしっかりと基づいたマネジメントを行なっていくことが求められるのです。
この本質を理解した時、これまでなぜか行き詰まっていた道が開けてくるかもしれません。
目的を持って始める
当たり前のようなことですが、意外と見落としがちなこの習慣を、是非とも意識していただきたいと思います。
ただ、
「わかっていてもできないこともある。何か具体的な解決策はないの?」
そう思われた方もいるかと思います。
コビー先生は、この目的志向を身につけるために、まずはミッションステートメントを立てることを勧めております。
ミッションステートメントとは、自身の核となる憲法のようなもので、何か行動を起こす時、悩んだ時などに、常にその中心となるものです。
詳細は書籍を読んでいただければと思いますが、私は自身の役割別にそれぞれミッションステートメントを立てました。
私個人、父親、夫、子供または兄弟、友人などの役割ごとに、自分のあるべき姿・こうありたいと強く願う姿をミッションとして定めます。
そして、それぞれに関わる内容について判断を迫られた時、その憲法に準じているか、目的からずれていないかを見返すようにしています。
こうすることで、無駄なことはしないで済みますし、自分の憲法に従っているので誰かのせいにすることもありません。
みなさんもまずはミッションステートメントを立てるところから始めてみませんか?
第三の習慣「重要事項を優先する」
これも当たり前のようで、なかなか実践するには骨が折れる習慣です。
コビー先生曰く、全ての活動は以下の4つに分類されます。
- 重要で緊急なこと
- 重要だが緊急ではないこと
- 重要でないが緊急なこと
- 重要でなく緊急でないこと
そして、私たちが優先すべきは圧倒的に2の重要だが緊急でないことだと言います。
ちなみに2の活動には、誰かとの関係性を育んだり、自己研鑽であったりが含まれます。
確かにこれを優先すべきと言うのは、なんとなく想像がつきますよね。
ですが、私たち社会人のほとんどが1の重要で緊急なこと(締め切りが近い仕事、家事など)に忙殺され、余った時間を4の重要でなく緊急でないこと(SNSの閲覧、youtube視聴など)に割いて1日が終わってしまいます。
こんな毎日を送っていたら、到底2の活動を行うことはできません。
コビー先生は、まず自分にとっての2の活動とは何かを明らかにし、その活動をスケジュールに優先的に入れ込め!と厳しく言います。
1日は等しく24時間しかなく、1と4の活動でパンパンになっている現状で、「時間があったらやろう。」などと思っていても、到底2の活動はできないのです。
私にとっての2の活動の一つに、子どもとの戯れ(関係性構築)があります。
これまでは、それに割く時間が重要だと頭でわかっていても、仕事から帰って家事に追われ(1の活動)、息抜きにコーヒーを飲みながらスマホをぽちぽちしてしまい(4の活動)、気づいたら子どもとしっかり向き合う時間もないまま1日を終えていました。
7つの習慣を読み、2の活動を優先させることの大切さを実感した後は、帰宅後スマホを寝室の充電器に刺して、基本的には見ないようにしました。
すると4の時間が削れ、余った時間の分だけ子どもとの戯れに時間を捻出することができるようになりました。
そして、1日を終えた後の満足感は、はるかに向上しました。
ほんのわずかな変化でも、2の活動を優先する意識を持つことで、生活、人生の満足度は大きく変わってくることを実感できますよ。
最後に
いかがだったでしょうか。
今回は『7つの習慣』より第一〜第三の習慣を紹介させていただきました。
少しでも納得感があった方は、是非とも書籍を手に取って、何か一つでも実践してみていただければと思います。
自分の人生を大きく変えるには、習慣から変えることが大切です。
何かを変えたいと思っている今こそ、習慣を見直し、一歩でもなりたい自分に近づいていきましょう。
ではまた!
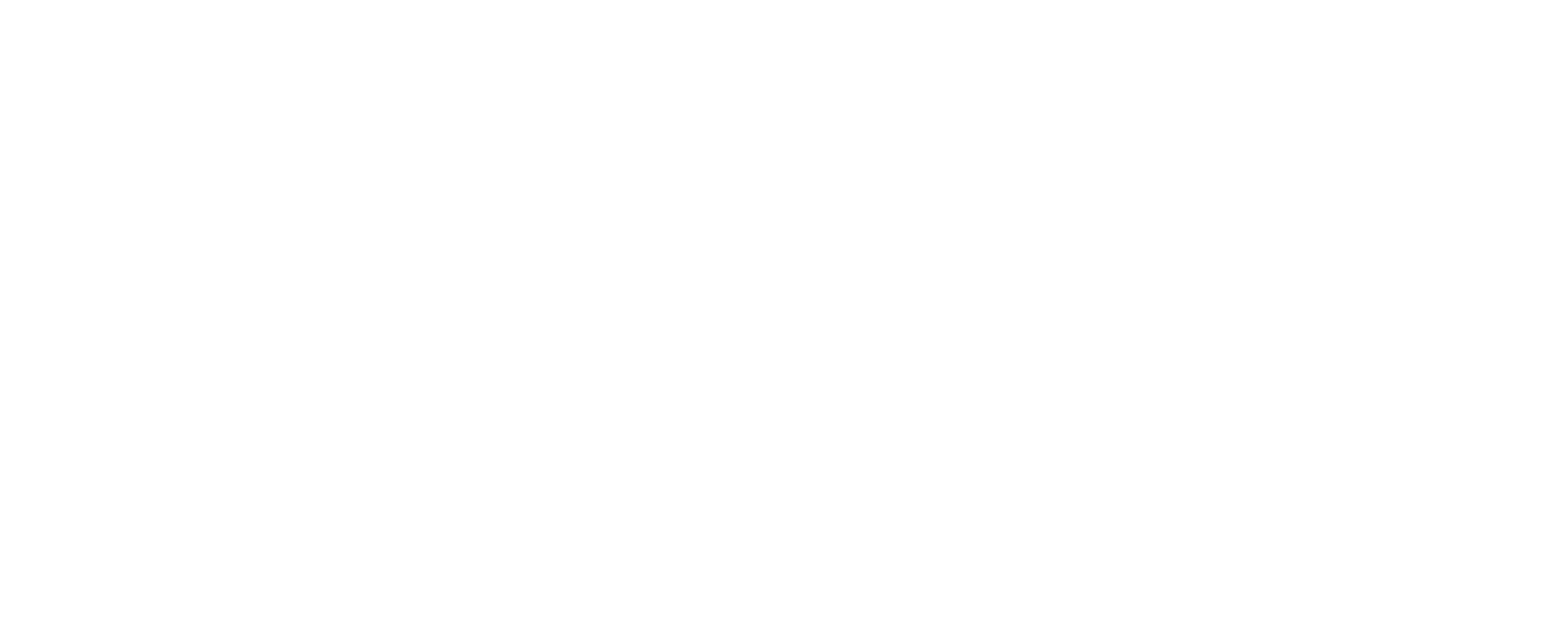





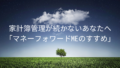

コメント